
【保護猫ふくちゃんとの生活 vol.20】最初は少し不安だった2匹飼育…今では仲良し“ふくぼん”コンビに
保護猫ふくちゃん & ぼんちゃんと共に、2匹と2人で仲良く暮らしている筆者。我が家の2匹目、ぼんちゃんを昨年末にお迎えしてから、半年が経ちました。
動物のリアルを伝えるWebメディア

日本獣医生命科学大学獣医保健看護学科(東京都武蔵野市)は、3月4日付けで「愛玩動物看護師法」に規定される「農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を開講する大学」として発表された。

ペットの予防医療の啓発・普及活動を展開する獣医師団体「Team HOPE」は、犬と猫の飼い主・家族412人を対象に、「ペットの健康管理に関する実態調査」を実施、その結果を発表した。
![飼い主の笑顔と動物の幸せのために…ペット用の義足・装具という選択肢[インタビュー] 画像](/imgs/p/hSRUyJCK9L6K4aRtNr4I8ZuYPJaO8JU3k4mQ/24495.jpg)
ペット用の各種装具や義足の開発・製造を行う会社が東京都町田市にある。東洋装具医療器具製作所の代表、島田旭緒(あきお)義肢装具士にペット用の装具について聞いた。

新薬を使ったがん治療や「問題行動」を獣医学の観点から治療する「行動診療」など、最先端の獣医療を紹介。また、日常で必要となり得る夜間診療や輸血治療などは、「もしも」の時に慌てないよう覚えておくことが安心につながる。

アニコム ホールディングスは、ペットの疾患統計などをまとめた「アニコム 家庭どうぶつ白書2021」を公開した。犬猫だけでなく、鳥・うさぎ・フェレットのほか、エキゾチックアニマルの平均寿命も初めて掲載している。

麻布大学生命・環境科学部食品生命科学科の島津德人准教授(食品生理学研究室)の研究グループは、よみうりランド・アシカ館(東京都稲城市)と共同で、アシカの歯周病の研究を展開している。
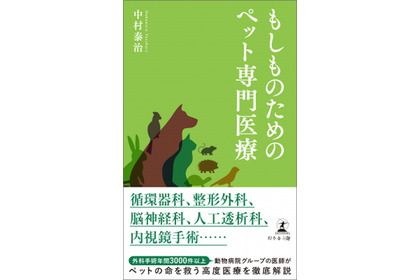
幻冬舎メディアコンサルティングは、『もしものためのペット専門医療』を11月1日に刊行した。

キツネや犬の糞を媒介に、ヒトが感染することもあり得る「エキノコックス症」。国立感染症研究所は、近年相次ぐ野犬の感染確認を受け、愛知県南部の知多半島で「定着した」との見解を示した。10月12日付の福井新聞が報じた。

栄養学に基づいた犬と猫のプレミアムペットフードおよび食事療法食を展開するロイヤルカナン ジャポンは、犬と猫のペットオーナーを対象に「愛犬・愛猫の健康診断受診に関する実態及び意識調査」を実施し、その結果を発表した。
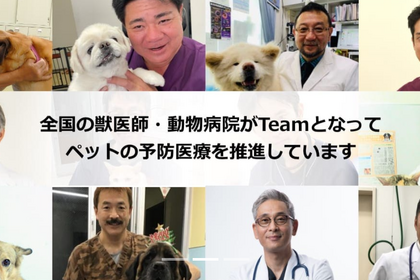
ペットの健康診断を推進する獣医師団体Team HOPEは、ペットの高齢化が進む中、健康寿命の延伸を目的に予防医療の大切さを啓発している。

これまで2回にわたり、狂犬病ワクチンに関する最新の獣医学的研究結果を紹介した。今回は疫学の観点から、専門家が提案する包括的な狂犬病予防対策の考え方を紹介する。