これまで、狂犬病に関しても抗体検査が有効であることと、ワクチンの効果が1年以上続くと主張する専門家の意見をご紹介してきました。
一方で、狂犬病の場合は抗体検査での陽性結果が病気から守られている状態である保証はないとも言われています。今回は、その考え方について触れます。
抗体値と免疫との関係に対する微妙な言い回し
「北米獣医師コミュニティ」(筆者訳、NACV)が発行する「TODAY'S VETERINARY PRACTICE(臨床獣医療)」は、狂犬病ワクチンと抗体検査に関して触れています。ノースカロライナ州立大学・獣医学部のリチャード・フォード名誉教授が2013年に出したステートメントを引用しています。
「検査方法に関わらず、狂犬病の抗体検査結果は防御能(= 病気から守る力)との直接的な相互関係はない。したがって、免疫があるかどうかの法的指標と判断することはできない。狂犬病の予防には、例えば細胞性免疫など抗体以外の免疫機能も重要である。とはいえ狂犬病の抗体価が『陽性』であることは、ワクチン接種後に免疫反応が生じたことは間違いなく証明している。したがって抗体価は免疫防御能との間に相互関係があるとみることもできるが、法律上は、ワクチン再接種の代わりに使用することはできない」
できるだけ正確に訳してみました。法律が関係するためか、かなり難解な表現があえて使われている印象を受けます。簡単に言うと、下記のような内容だと思います。
「抗体検査で狂犬病に対して陽性になったということは、過去にワクチン接種で免疫反応が起きたのは間違いない。よって、狂犬病に対する免疫が働いているとみることも可能である。しかしながら、法律的にはそれによってワクチンを打たなくていいとは認められない」
「アメリカ獣医師会」(AVMA)も、定期出版物で同様の立場を表明しています。
「狂犬病抗体検査について:地域によっては動物の持ち込みに狂犬病ワクチン接種と抗体検査の証明書提示が必要となる。狂犬病の抗体価(陽性結果)はワクチン接種または(過去の)感染によって(免疫)反応が生じたことを示すものであるが、防御能とは直接的な相関関係がない。なぜなら、狂犬病の予防にはその他の免疫要素も役割を果たすからである。それらを測定・解析する方法は、まだ十分に開発されていない。したがって、動物の体内に狂犬病ウイルスに対する抗体があるという証明は、狂犬病予防のために行うワクチン接種の必要性を判断することには使用されるべきではない」(カッコ内は筆者による追記)
要するに、狂犬病の場合はウイルスに対する抗体があっても、つまり陽性でも、病気の感染から守られているとは必ずしも言えないという判断です。この根拠としてAVMAは4本の論文を出典として提示しています。その中の最も新しい物を検証してみました。
抗体検査手法が明確には確立されていないとの主張
ジョージワシントン大学(GWU)のジェフリー・ベソニー教授らが2010年に発表した「狂犬病の抗体について」と言う論文がそれです。これは、アメリカ国立医学図書館が保有する関係論文を「PubMed(パブメド)」という国立衛生研究所が運用する無料検索エンジンで探してリビューした結果をまとめたもの。対象となった論文は、1975年から2008年までに発表されたものだそうです。
結論として、狂犬病ウイルスから体を守ることにおいては、抗体が中心的な役割を担うことは認めています。ただし、生体内で実際に生じている反応はとても複雑で、現在確立されている抗体検査とその評価方法で分るのは「多くの場合、病気を防ぐしくみの部分的なものに限定される」としています。ベソニー教授はまた、WHO(世界保健機構)などが認めている抗体検査の方法(RFFIT法:迅速蛍光焦点抑制試験法)が抗体価を計る「Gold Standard (黄金律)*」としながらも、命に関わるリスクがある狂犬病については検査と評価の方法を選ぶことには慎重であるべきだとしています。
* 診断や評価の精度が高いものとして広く容認された手法
余談になりますが、GWUは政治の中心である首都ワシントンDCにある名門大学です。場所柄、政治家や官僚などの経験者が教鞭をふるっていることでも知られており、ロビー活動などに関する知見も豊かです。動物の狂犬病に対する免疫というテーマが、獣医学で世界的に有名な、例えばカリフォルニア大学デービス校などからでなく、GWUから出されている事実には興味を感じます。
世界中で採用されているWHO基準
そのGWUが疑問を投げかけている抗体検査・評価手法ですが、この特集のvol.2でご紹介したようにWHOは有効としています。狂犬病ウイルスに対する抗体価を測定し0.5 IU/mL以上あれば狂犬病ワクチン接種後の適切な免疫応答と判断できるとしています。この場合の検査方法がRFFIT法です。
また、RFFIT法は、人間に接種する狂犬病ワクチンの評価や認証においても世界中の公的機関で採用されています。新薬の効果やリスクを調べる治験では、被験者(人間)に狂犬病ワクチンを接種し、その後、採血します。RFFIT法による抗体検査で0.5IU/mLの基準を満たせば、そのワクチンには予防効果があると判断されます。最も慎重に判断されているはずの人間の場合も、狂犬病ウイルスに対する抗体検査は確立されていると考えられます。
日本における狂犬病ワクチンの認証もWHO基準を使用
もちろん日本も同様です。世界的な製薬会社の日本法人であるグラクソ・スミスクライン株式会社が2019年に狂犬病ワクチンの製造販売承認を厚生労働省から取得しました。その際も、有効性などに関して行った臨床試験結果は全てこのRFFIT法による抗体検査によって評価されています。
前提として、「WHOはRFFIT法にて狂犬病ウイルスに対する中和抗体価を測定し、0.5IU/mL以上あれば狂犬病ワクチン接種後の適切な免疫応答レベルとしている」とあります。また、「狂犬病ウイルスに対する中和抗体価が (独立行政法人医薬品医療機器総合機構が公表している「乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチンラビピュール筋注用 臨床に関する概括評価」より)
賛否両論を検証したうえで
グラクソ社の例は人間に接種する狂犬病ワクチンに関するものではありますが、接種の有効性と再接種の必要性は抗体検査によって判断するのが世界中で認められた手法になっています。ベソニー教授が主張するように、命に関わる狂犬病の場合はその効果の検証には慎重な判断が必要だとは思います。しかしながら、以前ご紹介したウィスコンシン大学のロナルド・シュルツ名誉教授らによる論文(vol.5参照)は、実際に犬を使って感染するかどうかを確認した「チャレンジ試験」の結果に基づいています。さらに、ベソニー教授の慎重論よりも新しく2016年に発表されています。
次回は、北米で狂犬病ワクチンについて言われている興味深いエピソードをご紹介しつつ、そこから感じたことをまとめます。






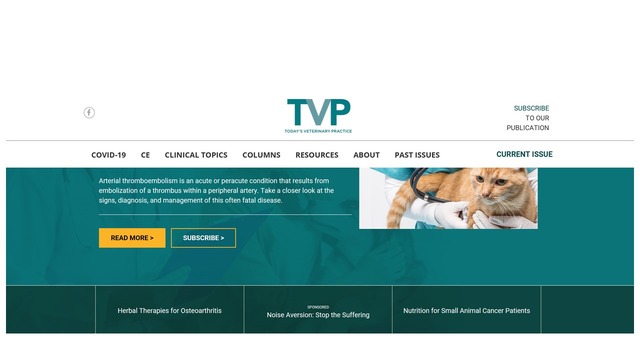
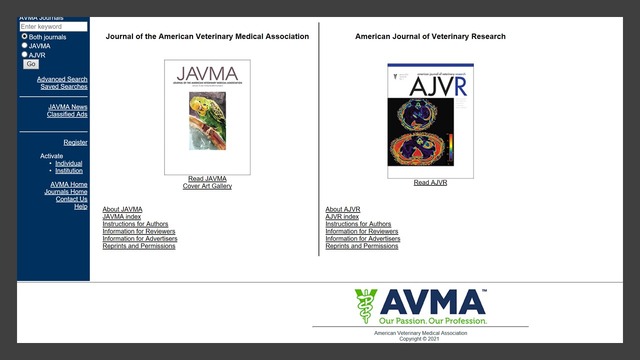








![「獣医師の視点で調べやすさにこだわった」犬猫のオンライン医療事典[インタビュー]](/imgs/p/z4qwkiDmZkrj0snJy7poXZuYHpaSlZSTkpGQ/32160.png)






