前回は、狂犬病ワクチン接種に関する北米の状況について見てみました。
アメリカでは、多くの州で狂犬病ワクチンの定期接種が法律で決められていますが、法的義務がない地域も存在します。また、健康上の理由による免除も州によって異なります。さらに、対象動物や接種頻度なども統一されていないことが分かりました。一方カナダでは、狂犬病予防注射の接種が法律で強制されるのはオンタリオ州だけであり、考え方が大きく異なることが分かります。
今回は、このことを念頭に置きながら、アメリカで狂犬病ワクチンの定期接種にエビデンスを提示しながら警鐘を鳴らす獣医師の主張をご紹介します。
地域ごとに法規制の違いがある理由の1つとされる考え方
国ごとに、また地域によって法律の定めは一律でなく考え方は様々です。この理由の1つとして、主な感染源がペットか野生動物かの環境要因によるアプローチの違いとするものもあるようです。野生動物からの感染リスクが高い地域では、ペットへの予防接種よりも野生動物との接触機会を減らすことに重きを置いているという話があります。しかしながら、いずれの場合も人間に最も身近な動物がペットであるのは間違いありません。主な感染源が野生動物であることを理由に、犬や猫へ予防接種を「しない」と判断しているとは考えにくいのではないかと思います。
疑問に感じる「例外ない1年に1回のワクチン接種」
検証が必要なのは予防そのものではなく、定期的な、例外ない、機械的な接種。いずれにしても、発症した場合の死亡率がほぼ100%という恐ろしい感染症を予防することに、議論の余地はありません。ワクチンの大切さについてはこのシリーズのvol.1でご紹介しました。繰り返しになりますが、疑問に感じるのは、日本の場合「例外なく1年に1回のワクチン接種」と決められていることです。
狂犬病ワクチンの接種法に意義を唱える専門家の存在
狂犬病ワクチンの重要性については既に多くが語られているので、今回は否定的な意見をご紹介します。ワクチン接種そのものに対してではなく、現在のやり方、つまり、例外なく定期的に接種を行うという行為に対して疑問を呈するものです。ワクチンにおいては人間用の開発でも重要とされていますが、常に「リスク・ベネフィット評価」が重要です。
ワクチンの過剰接種に警鐘を鳴らす獣医師
アメリカで活躍しているカレン・ベッカー獣医師は、ワクチンが動物を病気から守ってくれる期間(免疫持続期間:DOI)に関する科学的な検証不足を指摘しています。「…ごく最近まで、獣医師の世界ではこの分野の研究が事実上無視されてきました。『動物用ワクチンの毎年接種』と言うガイドラインは数十年前に設定され、それを作ったのはワクチンメーカーなのです」とのことです。
人間には有効な抗体検査
また、人間が打つ狂犬病予防注射に関しては抗体検査が有効とされているそうです。「…私たちすべての獣医師は狂犬病予防接種を受けなければなりません。その後は狂犬病に対する抗体検査を受けます。毎年、自動的にワクチンを打つわけではありません」として、動物への狂犬病ワクチン接種も同様の扱いであるべきだと語っています。
「科学的根拠に基づかない法律」
さらに「抗体検査」で陽性が確認されても接種が免除されない法律を、科学的根拠に基づかないと言っています。「狂犬病ワクチンの接種は法律で義務化されているため、抗体検査で陽性が確認されても病気から守る免疫があると - 法的には - 解釈されません。科学的根拠に基づかない法律が、狂犬病に対する免疫を既に持ったペットに繰り返しワクチン接種を行うことを強要しています。こうしたワクチン接種は、役に立たない - つまりペットの”免疫力をより高める”ことにはならない - と同時に、場合によっては害になり得るのです。」(筆者訳;healthy pets 2020年8月23日)
エビデンスに基づいたワクチン接種を明確に主張する獣医師
アメリカには、より積極的に狂犬病ワクチンの過剰接種に注意喚起を行う専門家もいます。ウィスコンシン大学マディソン校・獣医学大学病理学部のロナルド・シュルツ名誉教授によれば、狂犬病に対する抗体検査で陽性が確認された犬には、抵抗力が7年は持続していることが確認されたそうです。2016年2月、シュルツ教授が「関係各位」宛にウィスコンシン大学として出した声明には以下が明記されています。(要点を筆者が翻訳)
・アメリカ疾病予防管理センター(CDC)の指導により、狂犬病への感染リスクが高い職業従事者は2年ごとに抗体検査を受ける。抗体価が基準を満たせば狂犬病に対する免疫があると判断され、ワクチン接種は行っていない
・ほとんどの地域で動物の抗体価に関わらず毎年または3年に1度の狂犬病ワクチン接種が求められている。「これは科学的に欠陥のあるアプローチ!」である。ワクチン接種の目的は、病気を安全に予防することでなければならならず、単に行政上の要求などを満たすためであるべきではない
・ペットへの狂犬病ワクチン接種は公衆衛生上必要不可欠だが、死亡を含む副反応などのリスクは避けられない。そうした症例は多くないが、抗体によって既に狂犬病から守られていると判断できる動物をリスクに晒すのは不当なものである
・狂犬病ワクチンの成犬への再接種に関しては、まず抗体の状態を確認すべきである。その上で、感染リスク(筆者注:生活環境などウイルスに接触する機会が高いのかどうかなど)を検討し、必要な場合に再接種を行うのが科学的に意味のある方法である。これは、人間では既に標準となっている
・動物用狂犬病ワクチンの効果を確認するため、狂犬病ウイルスを動物に接種する実験を行った。過去に2回の狂犬病ワクチン接種を受け、抗体検査で陽性が確認された場合は狂犬病への抵抗力が7年は持続していることが確認できた
(ウィスコンシン大学マディソン校・獣医科大学病理学部発行のレターより)
ワクチンによる免疫が何年も続くことを研究で実証
シュルツ名誉教授は、1970年代半ばから狂犬病を含む犬用のワクチンを研究しています。2006年には、様々なワクチンによってもたらされるDOIに関する論文を発表しています。その中で、狂犬病ワクチンは接種後長期間にわたって犬をこの病気から守るとしています。
「チャレンジ試験」結果を論文で発表
オランダにある国際的な出版社「エルゼビア」が運営する、査読済み論文を掲載する「サイエンスダイレクト(ScienceDirect)」にこの論文が掲載されています。研究では、ワクチンを接種した約1000頭の犬を対象に継続的な抗体検査を行ったそうです。並行して、一部の犬たちには「チャレンジ試験」を行い実際に発症するかどうかを確認したとのこと。
チャレンジ試験というのは、接種後に病原体に晒すことでそのワクチンの有効性を評価する試験手法の1つです。例えば狂犬病ワクチンを打った後、その動物に狂犬病ウイルスを注射して発症するかどうかを確認します。試験の結果、ワクチン接種後の「最低3年」は狂犬病から守られたそうです。なお、ジステンパーウイルス、アデノウイルス、パルボウイルスに対しては最低7年という結果が出ています。
ワクチン接種は手術などの医療行為と同様、医学的判断によるべき
同教授によると、「抗体は犬用のコアワクチン、すなわちジステンパーウイルス、パルボウイルス(CPC-2)、アデノウイルス(CAV-1)および狂犬病ウイルスへの主要な防御免疫メカニズムである」としています。「(狂犬病を含む)犬用コアワクチンの場合、再接種の間隔を延ばしても病気に罹る危険性は増えない。また、それによって(= 注射の回数を減らすことで)副反応のリスクは確実に減る」として、手術などと同様、ワクチン接種も獣医学的に必要と判断された場合にのみ行うことを推奨しています。
次回は、同様のテーマについて、世界的な獣医師団体による見解についてご紹介します。





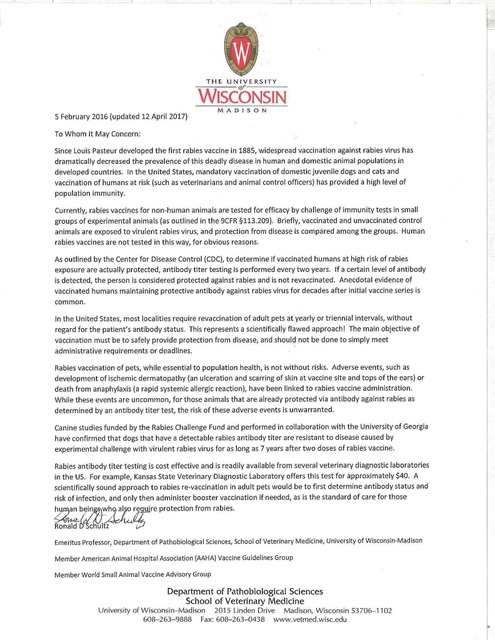
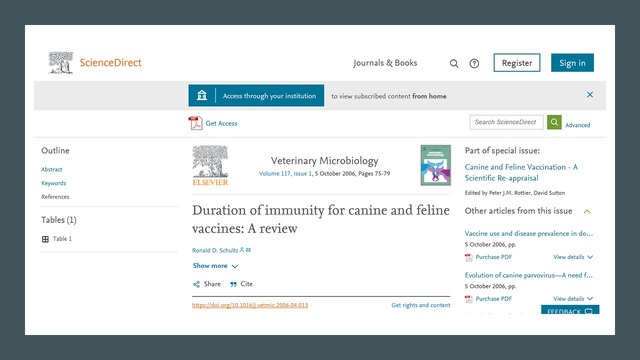







![「獣医師の視点で調べやすさにこだわった」犬猫のオンライン医療事典[インタビュー]](/imgs/p/z4qwkiDmZkrj0snJy7poXZuYHpaSlZSTkpGQ/32160.png)






