
【保護猫ふくちゃんとの生活 vol.20】最初は少し不安だった2匹飼育…今では仲良し“ふくぼん”コンビに
保護猫ふくちゃん & ぼんちゃんと共に、2匹と2人で仲良く暮らしている筆者。我が家の2匹目、ぼんちゃんを昨年末にお迎えしてから、半年が経ちました。
動物のリアルを伝えるWebメディア
![【獣医療の最前線】獣医動物行動学とは?…犬や猫の「問題行動」を獣医学的に診断・治療[インタビュー]vol.1 画像](/imgs/p/hSRUyJCK9L6K4aRtNr4I8ZuYPJaO8JU3k4mQ/10649.jpg)
今回は、動物の「問題行動」を獣医学的な観点から診断・治療する「獣医動物行動学」についてご紹介します。東京大学・獣医動物行動学研究室の武内ゆかり教授にお話をうかがいました。

犬用のいわゆる「混合ワクチン」について、これまでリスクの最小化と効果の最大化を図る最新の考え方をご紹介してきました。今回の特集では、狂犬病ワクチンの必要性とリスクについて考えていきます。

愛犬ルナが進行の早い移行上皮癌との診察を受けて「終活が始まる」という事実が突きつけられました。これまでの生活に後悔は多々あれど、今現在を後悔しないようにする生活が始まります。

シニア期からハイシニア期にかけては、愛犬に様々な体の変化が現れます。そんな変化の中で特に注意したいのが「認知症」(認知機能不全症)です。今回はワンちゃんの認知症について症状や予防、治療法などを、動物看護師の筆者が前後編にわたってお届けします。

これまで2回にわたり、人間による繁殖が原因で犬が苦しむケースを紹介した。今回は遺伝的疾患のリスクが分かっていながらも標準と認められるケースについて触れる。その上で、我々日本に暮らす一般の飼い主がどうすべきかについて、考えたい。

前回は、イギリスの関係者が同国内におけるブリーディングには「依然として課題が多い」と語ったことについて触れた。今回は、その課題と世界的な「犬種標準」について紹介する。

これまでこのシリーズでは、「コア」に分類されるワクチンの免疫が少なくとも3年は持続するため毎年の接種は基本的に不要なことをご紹介しました。最終回の今回は、改めて世界的な専門機関が提唱しているワクチン接種の考え方をご紹介します。

REANIMALではこれまでに、犬のブリーディングについて様々な角度から検証した。今回は、これまでに紹介したことを含め人間が「創り出した」身体的苦痛に苦しむ犬たちについて3回にわたって考える。
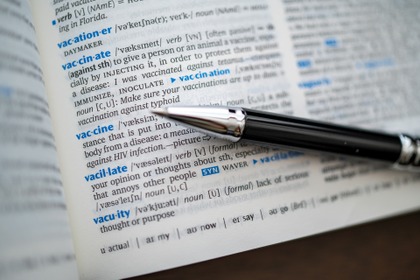
前回までに、ワクチンは必要なものを必要な時に接種することが愛犬の身体を守る上で安心・安全なことをご紹介しました。今回は、副作用の怖さについてご紹介します。

前回、これまでご紹介してきた犬用のワクチンについて、ポイントをまとめました。今回は、筆者の愛犬に実際に起こったできごとと、そこで改めて感じた安心で安全なワクチン接種についてご紹介します。

このシリーズでは2回にわたって犬と猫の遺伝的疾患リスクを発見するための遺伝子(DNA)検査について触れた。最終回となる今回は、遺伝子検査によって生じると考えられる社会的なリスクと、その上で、私たち一般の飼い主ができることについて考えたい。