
【保護猫ふくちゃんとの生活 vol.20】最初は少し不安だった2匹飼育…今では仲良し“ふくぼん”コンビに
保護猫ふくちゃん & ぼんちゃんと共に、2匹と2人で仲良く暮らしている筆者。我が家の2匹目、ぼんちゃんを昨年末にお迎えしてから、半年が経ちました。
動物のリアルを伝えるWebメディア

人間やワンちゃん程広く認知されていませんが10歳を超えた猫ちゃん達は少しずつ認知力が落ちてくると言われています。そこで今回は、具体的な症状や対策についてご紹介します

ルナの癌が発覚してから飼い主の生活は大きく変わりました。コロナの影響もあり、共に過ごす時間は格段に増えて寝るのも一緒。そこだけを切り取れば幸せなのですが、やはり癌は待ってはくれませんでした。

犬への狂犬病ワクチン接種について考える特集の第3回。今回は、北米の2ヵ国(アメリカ合衆国とカナダ)の状況について紹介します。

2021年、新春のスタートは、コロナ禍真っただ中。愛犬とのドライブ旅行を計画していた愛犬家のみなさんも、Go To トラベルの一時中止や様々な不安から、自粛、キャンセル…といった、ストレスのたまる生活を送っているのではないだろうか。
![【獣医療の最前線】飼い主がペットと向き合う上でのアドバイスは?…獣医動物行動学編[インタビュー]vol.3 画像](/imgs/p/hSRUyJCK9L6K4aRtNr4I8ZuYPJaO8JU3k4mQ/11057.jpg)
これまでペットの「問題行動」について、2回にわたって東京大学・獣医動物行動学研究室の竹内ゆかり教授にお話をうかがいました。最後に、一般の飼い主さんが知っておくと役に立ちそうなポイントについて、アドバイスをいただきました。

本連載では、令和元年11月に生まれた筆者の長女と4才の保護猫の暮らしを綴っています。今回は、生後6か月を迎えた娘を初めて猫カフェに連れて行ったときのエピソードです。
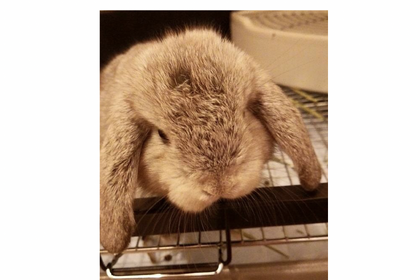
「けだま」の残してくれた、飼育環境やウサギとの生活での注意点などの知識のおかげで、不安を感じることなくスタートした「けまり(まー様)」との新しい生活。驚いたのは全く別の生き物と言っても過言ではないレベルでの、性格の違いでした。
![【獣医療の最前線】受診する飼い主の悩みは攻撃行動や常同障害、トイレ問題など…獣医動物行動学編[インタビュー]vol.2 画像](/imgs/p/hSRUyJCK9L6K4aRtNr4I8ZuYPJaO8JU3k4mQ/10657.jpg)
「問題行動」を獣医療の観点から診断・治療する「獣医動物行動学」。今回は、東京大学附属動物医療センターの行動診療科で武内ゆかり教授が診察してきた症例についてうかがいました。

前回は、死亡率がほぼ100%という狂犬病の恐ろしさと、予防の大切さについてご紹介しました。そうした点は十分に認識した上で、この特集では接種の頻度を下げられないのかについて検証。今回は、免疫とワクチンによる予防の仕組みを解説します。

「猫伝染性腹膜炎(FIP)」は急激に症状が進み、10日前後で死に至る病気だ。現在のところ確立された治療方法はない。そんな中、新型コロナウイルス感染症治療薬である「レムデシビル」が治療薬として有力視されている。

いざ愛犬に認知症の症状が出てきたとき、自宅でできることや治療にはどういったものがあるのでしょうか? 具体的な症状と合わせて紹介していきます。